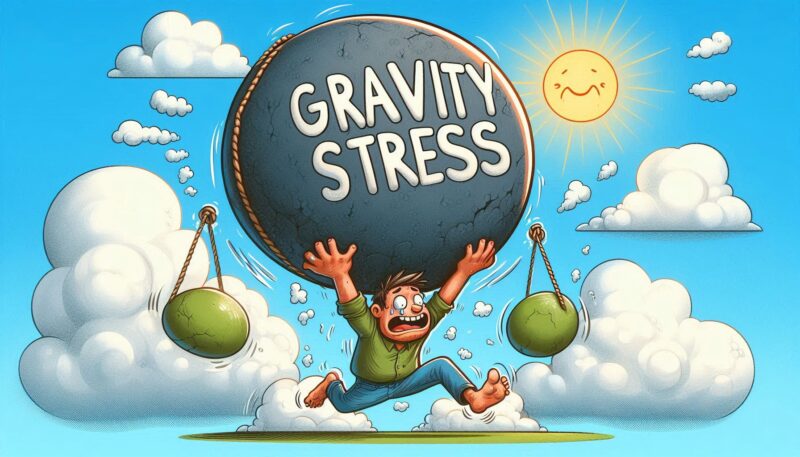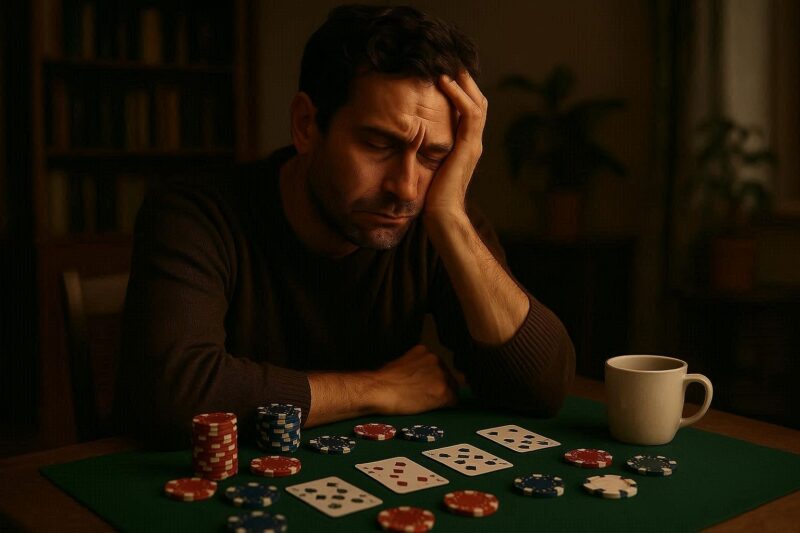ストレス 効く食べ物 ストレスを感じたときに積極的に摂るといいものがあるのでそれを紹介します。相当なダメージでストレスがかかってしまったときは、絶食したほうが効果的な場合がありますが、そうでなければ次に紹介するものを食べると元気になり、ストレスに打ち勝つよいきっかけになります。
ストレス 効く食べ物
基本的には特定の食べ物がストレスを直接的に解消するわけではありませんが、栄養バランスが整った食事は身体や脳の健康に寄与し、ストレスへの対抗力を高めることができます。以下は、ストレスに対抗するのに役立ついくつかの食べ物です。
ビタミンCでストレスに強くなる
 ストレス 効く食べ物
ストレス 効く食べ物
季節の変わり目や特に春先のストレスは、人の体にさまざまな変調を及ぼすものです。肌荒れや胃潰瘍、高血圧などはその典型で、さまざまな栄養素が消耗されて、体に悪影響が出てくるのです。
そうしたひずみをもとに戻そうと、体は副腎皮質ホルモンという成分を盛んに分泌し、懸命にストレスに抵抗しています。
ストレスに強い体をつくるには、この機能をしっかりはたらかせる必要があります。そのときおおいに役立ってくれる栄養素が「ビタミンC」 です。「ビタミンC」 は、ストレスに対抗する機能をはたらかせるときのエネルギー源になってくれます。ビタミンCが欠けると、ストレスに負けやすい体になるから、果物などから意識してとるようにします。
ビタミンCを多く含む食品
カルシウムをもっと手軽に摂る
 カルシウム補給にヨーグルト
カルシウム補給にヨーグルト
カルシウムは、ストレスの影響で失われやすい栄養素の代表格です。精神を落ち着かせるはたらきがあるので、足りなくなると、イライラしやすくなります。てっとり早く補給しようと思ったら「ヨーグルト」を食べるのがおすすめです。おやつのときはスナック菓子ではなく、カルシウムたっぷりのヨーグルトや牛乳をとるといいでしょう。
ヨーグルトや牛乳がどうも合わない人はこちらの「フジッコの善玉菌のチカラ カスピ海ヨーグルトの乳酸菌カプセル」。
3食の食事でしっかりカルシウムを摂りたいときは、煮干しなどの小魚をミキサーにかけた「カルシウムふりかけ」 を活用しましょう。ごはんにかけるだけでなく、みそ汁や酢の物などなんにでも入れられて、どんなメニューも栄養満点になります。日本人は、カルシウム摂取が不足気味です。
ひじきは優秀なストレス解消食品
 ひじき
ひじき
ストレスに効く食品のなかで、とくに優秀なのが、「ひじき」です。「ひじき」は、イライラに効果的なカルシウムが豊富にふくまれているだけでなく、カルシウムを効率よく吸収するためのマグネシウムも、バランスよくふくまれています。
食品にふくまれているカルシウムは、体内に入ったものが、すべて吸収されるわけではない。効果的にカルシウムをとるためには、助っ人となるマグネシウムをいっしょにとるのがコツです。
だから、カルシウムをふくんだ食品を食べるときは、いっしょにマグネシウムをふくんだ食品「落花生」や「カシューナッツ」などのナッツ類を意識してとるといいでしょう。
「赤いビタミン」が心身に効く
 まぐろにはビタミンB12
まぐろにはビタミンB12
数あるビタミンのなかでも、造血作用のある「赤いビタミン」といわれるものがあります。マグロの赤身に多くふくまれているビタミンB12です。
ビタミンB12は、造血作用だけでなく、神経細胞のトラブルを改善したり、疲耕刀回復に目立った効果を上げることでも知られています。心身ともに疲れているときは、このビタミンB12が豊富にふくまれている食べ物をとると、ストレスに強い体になります。鶏レバーやシジミ、アサリなどのなかに、ビタミン12はたっぶりふくまれています。
イライラに効く野菜はこれ
ストレスとビタミン、ミネラルは切っても切れない関係にあります。ストレスがたまると、どうしてもそれらの消費が増えてしまいます。
つまり、ふだんから野菜や果物をしっかりとっておけば、イライラや不快な気分に悩まされることも少なくなるというわけです。
野菜のなかでも、とくに神経をリラックスさせてくれる効果が高いのは、タマネギ、ニラ、シソの3 つ。これらの野采は季節を問わず、お店にならんでいます。ストレスを感じている人は、積極的にとりましょう。
イライラを抑えるレシチンをとる
 レシチンが豊富な大豆
レシチンが豊富な大豆
現在の効果の高い精神安定剤が開発される前まで、レシチンといえば、神経の安定剤につかわれていた物質です。
レシチンは、あまりなじみのない名前かもしれないが、チョコレートやアイスクリームをつくるときの添加剤としてむかしからつかわれています。
この場合は、水と油の分子をなめらかに混ぜ合わせる作用を活用しています。そうした性質のあるレシチンに、イライラを抑える効果があることもわかって、むかしは純粋に精製されたものが、安定剤につかわれていたわけです。もちろん、添加物や薬としてとらなくても、天然のレシチンが豊富な食べ物があります。大豆と卵の黄身がそれで、イライラや不快戒心が絶えない人にはおすすめです。
快適な眠りと目覚めのために ストレスVSサプリ